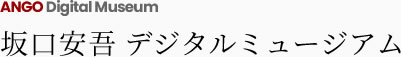作品
| 作品名 | 群集の人 |
|---|---|
| 発表年月日 | 1932/4/1 |
| ジャンル | 幻想・伝奇 |
| 内容・備考 | 一作ごとスタイルを変えた安吾初期作品のなかでも、特に異質な空気をまとった幻想譚。 ポーの短篇「群集の人」のタイトルをそのまま借用している。ポー作品は、都会の人々を観察するのが趣味の語り手が、気になった老人のアトをつけていくだけの話。都会の雑踏の中でしか安らぎを得られない、そんな病気があるとしたら老人はまさにそれだった。 ポーの小説以降、都会人は雑踏の中に混じっている時ほど自分が孤独であることを感じるようになった。ボードレールから萩原朔太郎まで、よく詩にうたわれたテーマで、ポーやボードレールを好んだ安吾も当然、早くからその孤独感に共鳴していた。 本作の斑猫(ハンミョウ)先生が孤独を愛し、「孤独には雑沓の街が好もしい」と思うのもポー作品へのオマージュだろう。 ぬめぬめとした闇を描くあたりの文章は、梶井基次郎のそれを思わせる。 「石造建築に籠つた冷気が妙に鋭く、併(しか)し澱んで液体のやうにヌルヌルと手頸に滑り顔になだれるやうであつた」 「耳のところに数字みたいのものが鳴り響いてゐる」 梶井作品は本作発表の前年に処女作品集『檸檬』が出たばかりだったが、『文科』同人の小林秀雄と三好達治が絶讃していたし、『青い馬』でも菱山修三が梶井論を書いていた。安吾も読んでいたことは間違いない。 梶井はドッペルゲンガー(自己像幻視)を幾度も自作に登場させた神経病的な作家だったが、それは安吾同様、やはりポーの影響下に生まれ出たモチーフであったろう。 ポーの「群集の人」には直接ドッペルゲンガーは出てこないが、群集に自我を融け込ませる心情とは、群集の一人一人が自分の分身とも見える感覚であり、趣向は同じだ。 大正から昭和初年代にかけて数多くの作家が、都会の夜にドッペルゲンガーを幻視した。芥川や梶井はその筆頭で、豊島与志雄、内田百間、富ノ沢麟太郎、渡辺温、野溝七生子、城昌幸らが繰り返しドッペルゲンガーを自作にもちこんだが、富ノ沢の「あめんちあ」に至っては最後に「お母あさん!」と叫ぶところまで安吾の本作と似ていた。 アイデンティティのゆらぐ瞬間、作家は未生以前の自分へと回帰するのかもしれない。 (七北数人) |
| 掲載書誌名 |